第1章 市民社会と墓地
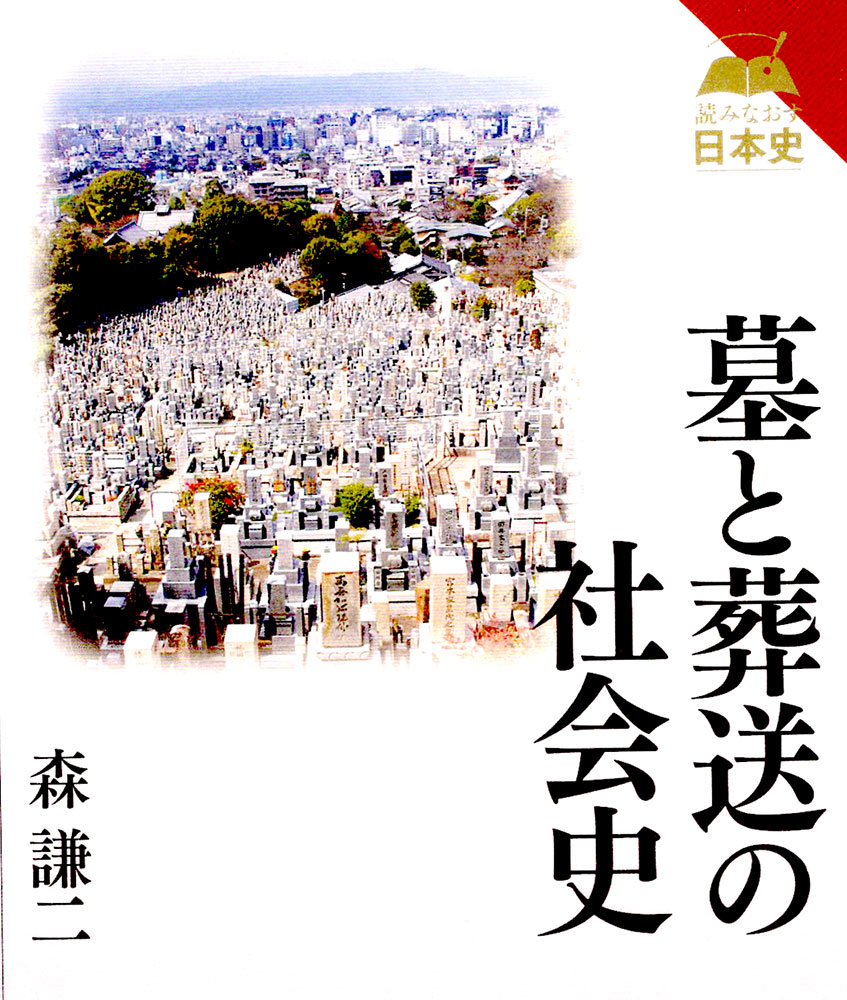 ■第1章 市民社会と墓地
■第1章 市民社会と墓地
■家族感情と墓
森 謙二(茨城キリスト教大学教授)
▶︎墓地のイメージ
墓地は、どのような意味をもった空間であり、どのような場所に設けられたのであろうか。また、人々は墓にたいしてのどのようなイメージをもっているのであろうか。


2006(平成18)年に東京都がおこなった「都民の霊園に関する意識調査」では「死者をしのぶところ」90%、「厳かなところ」38%、「明るい公園のようなところ」8.8%「単なる埋葬の場」11.9%、「暗く不気味なところ」10.3%となっている (複数回答)。
現在では、多くの人々が墓地を死者をしのぶところと答えており、墓地にたいして暗いイメージをもつ人々が少なくなっている。もちろん、この調査結果は東京都に居住する人々を対象とした意識調査であり、近代的な霊園をイメージして回答した人々が多いことを割り引きして考えなければならない。

それにしても、現在では墓地を「死者をしのぶところ」と考える人々が全体の四分の三にもなっているのである。彼らが「死者をしのぶ」という場合、彼らにとってその死者は縁もゆかりもない人々ではない。その死者は自分の親しい人たちであり、多くの場合、自分と生活をともにした家族の一員であった人々であろう。

墓地はそのような親しい死者を厳かにしのぶ場所なのである。また、現状の墓地の認識については「明るい公園のようなところ」とする人々が四分の一近くに達している。人々は墓地を、不気味な死霊がさまよう場所ではなく、親しい死者と再会をする舞台にふさわしい(明るい公園のような)空間であると、意識するようになった。
また、この調査では、一般に望ましい墓地の立地環境についても、「自然に恵まれた郊外」58.7%、「居住している地域の近く」22.6%、「市街地の緑地に隣接したところ」1人22%と、墓地を非日常的九完工間として社会から隔離する意識も希薄になつてきている。ここでも、墓地を「死積の場」として忌避するという意識は希薄になつていることがわかる。明るい公園のような場所であることを望み、他方では厳かな場所であることを望み、さらに社会から隔離されないことを望む。このような墓地空間は、親しい死者との再会の舞台であるだけでなく、(私)の「死後の住処」にもふさわしい空間なのである。
▶︎変化する慰霊形態
都市近郊の近代的な霊園のなかでも、「○○家之墓」と刻まれた(家墓)を数多くみいだすことができる。「○○家之墓」と刻まれた(家墓)の建立は、明治時代になり、火葬の普及や墓地拡張や新設の制限をつうじて普及しはじめるものであり、この(家墓)をもって日本の伝統的な墳墓の形態であるとは言えない。

もっとも、墳墓が(家墓)の形態をとるのが近代日本の産物であったとしても、家を単位とした墓地の形成は古くからみられたし、先祖代々が同じ墓地に眠るという枠組みの延長に(家墓)が形成されたものである限り、この(家墓)は伝統的な家の象徴として機能し、家的伝統を端的に表現するものであると言えるであろう。
そして、この(家墓)が、近代的な霊園のなかでも再生産されていった。それは、公園化した墓地のなかで墓地景観を保つという墓地造成上の問題から、また墓地不足を背景とした墓地区画の面積の制限という、外部的な要因にも基づいている。つまり、一つの墓地区画のなかには一つの納骨施設(墳墓)しか建設することができないことが多いからである。したがって、墳墓は合葬を前提とした(家墓)にならざるをえない。墓地経営のあり方が、(家墓)を規定してきたのである。
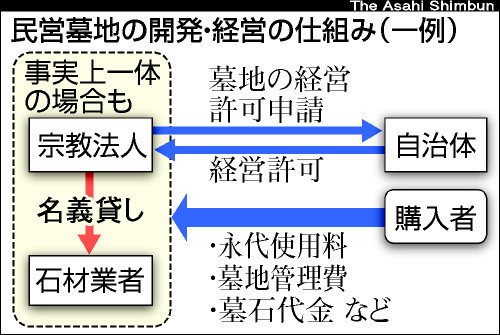
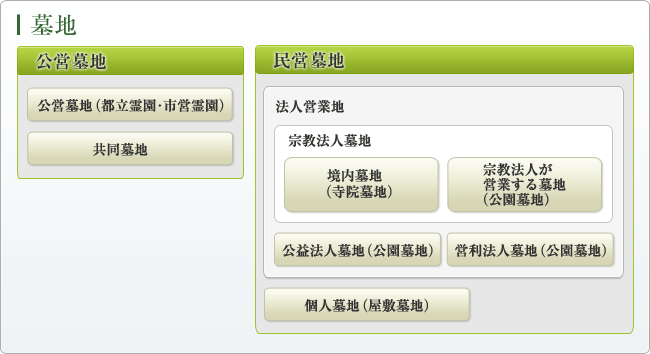
しかし、(家墓)についての意識は確実に変化していった。その変化は、生前に自分がはいる墓を手にいれようとする人々が多くなったことに表現される。生前墓(=逆修墓)は必ずしも現代的な現象ではないとしても、現在の民間霊園の墓地購入のうち、生前に自己の墓を購入するのが全体の6割から8割におよぶとされている。
つまり、現在、墓地を手にいれようとする多くの人々は、死者のためではなく、自分が「死後の住処」を確保するためにそれをおこなうのである。彼らは、当然、(私)が先祖の墓にはいることを期待するのではなく、(私)が子孫とともにはいることを期待しているのである。その「死後の住処」(私)を愛してくれた人々が詣り、この住処に(私)がかつて一緒に暮らした家族が住んでくれることを期待するのである。

さらに、墳墓(=石塔)に刻む言葉も変化してきている。かつて「○○家之墓」のように家名を刻んだ(家墓)から、「寂」「浄」「愛」「空」「夢」「憩」「和」など抽象的な言葉を墓碑に刻むケースも多い。もちろん、このよう言葉とともに(姓)を刻むケースが多いとしても、ここには祖先とともに眠る、あるいは祖先祭祀の対象としての墳墓という意識が次第に希薄になつてきていることが窺える。
家族との再会の舞台としての墓地には、かつての人々から隔離した「死穢(しわい・けがれ)の場」としてのイメージはない。さらに、墓地は先祖を祭祀するための空間であるという意識にも変化の兆しがみられる。
このような墓地イメージの変化を考えるとき、フランスの社会史家であるP・アリエスの考察が参考になるかもしれない。
▶︎他者の死
18世紀の後半になって、ヨーロッパでは公衆衛生の観点から都市内の墓地が批判の俎上(そじょう・ある物事や人物を問題として取り上げ、いろいろな面から論じたり批評したりする)に載せられ、18世紀末から19世紀にかけて都市郊外に新しい墓地の建設がはじまった。この意味では、この時期が、ヨーロッパの墓地の歴史にとって、大きな転換期であったともいえる。しかし、この転換は墓地形態の変化にとどまらなかった。教区教会から分離された墓地に、人々は参拝しはじめたのである。


この問題をアリエスは、「死を前にしての態度」(=「心性の変化」)としてとらえた。中世においては、死者は教会に委ねられたというより、教会に捨てられた、とアリエスはいう。中世後半になると、死者たちは自己の個別性を主張するようになり(=「自己の死」〉、14、5世紀になると、上層階層において家族用の礼拝所が設けられるようになる。しかし、ここが「死者の思い出」を確かめる場であるというより、まだ「名声を保つ配慮」のほうが重要であった、とする。
.jpg)

その後も、死にたいする態度の変化は確実に進んでいたこ19世紀以降になると、自己の死にはそれほどの関心を示さなくなり、特定の他者(家族)へ愛情を向けることによって「死とともに生きる」ことに満足をみいだすようになる(=「他者の死」)。この段階で、墓地はこの世で愛する者たちと再会をする舞台として用意されることになると、アリエスは論じている(『死と歴史」)。
家族とともに埋葬される傾向は、現在に至るまでヨーロッパ社会では続いている。二十世紀の後半になって、これまでとは異なった新たな傾向がみられるにしても、ヨーロッパ各地の墓地では(家族墓)が今なお一つの大きな流れを形成している。


アリエスの「死の文化史」は、祖先祭祀の観念が欠如したヨーロッパ(=キリスト教社会)の(死)と(墓)を問題としたものであるが、日本の社会にも部分的にあてはまる。ヨーロッパでは教会から墓地が分離されることによって、近代市民社会の墓地が形成された。この墓地はキリスト教から切り離されたものではないが、死者が宗教上の論理によってではなく、家族とのつながりのなかで埋葬されることを望むのである。


日本社会では(家族的なつながり)のなかで埋葬されることは、江戸時代以来庶民階層のなかでも一般的な現象になっていた。もっとも、この(家族的なつながり)は、家の枠組みを基礎にしたものであって、先祖代々の墓地に(先祖)とともに埋葬されることを期待したものであった「)この枠組みが払拭されたとはいえないが、現在の新しい墓地のなかで徐々に変化してきた。先祖とともに祀られるよりも、死者は、生前親しかった人々、自分とともに暮らした妻や子供たちと一緒に葬られることを望み、墓地は愛する者を失った家族がその死者を追悼する場になつたのである。死者は生前に自らが用意した墓地に埋葬され、そこで生前に愛した人々との再会を望むのである。
(家族的なつながり)のなかで近代的な墓地が形成されていくというのは、日本とヨーロッパではその内容において差異があるとしても、可視的には共通の現象として展開するのである。
Top
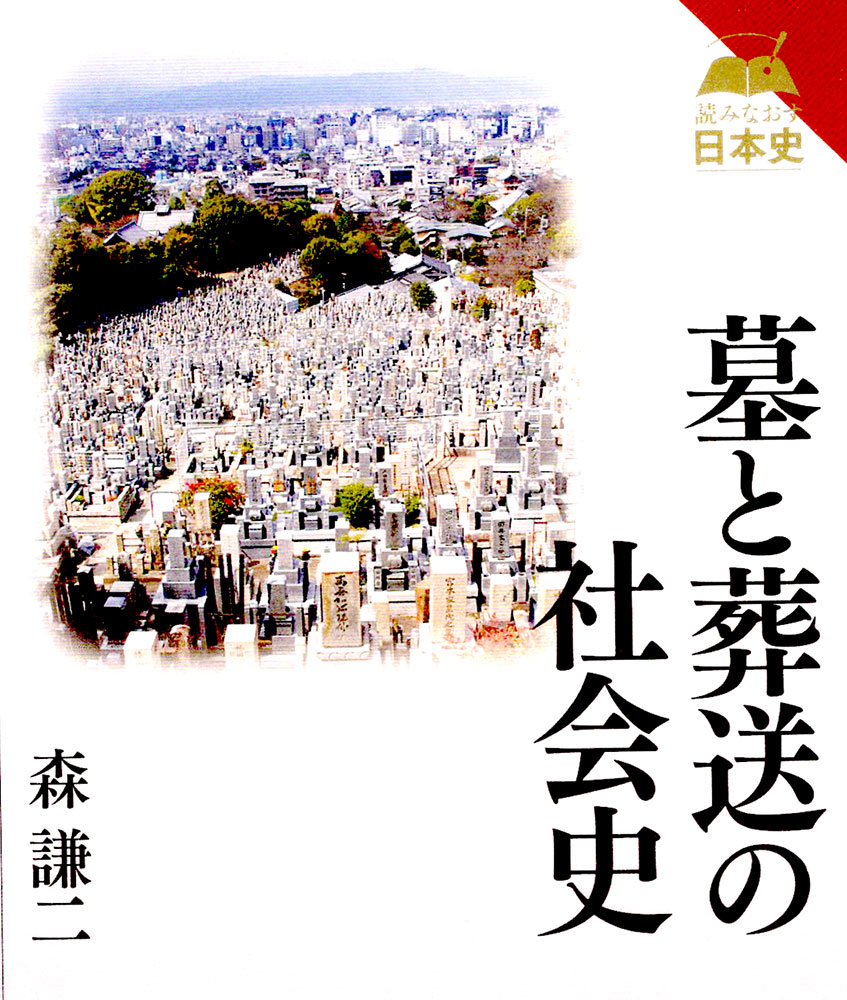 ■第1章 市民社会と墓地
■第1章 市民社会と墓地