■陽子ちゃんコロと通う(石岡駅-玉造町)鹿島鉄道
少女は陽子ちゃんといい、十七キロメートル離れた玉造町から鹿島鉄道に乗って石岡駅へ通っていた。飼い犬の名前は「コロ」、生後四か月で家にやってきた小犬だった。陽子ちゃんの両親は、陶器店を営んでいた。創業当初は食器類の店売りが主だったが、「丸忠」の屋号で建築資材やボイラーなどを取り扱う住宅設備会社へと事業を拡大していった。
父・丸島良昌(よしまさ)さんは大正十三年生まれで、陸軍士官学校出身のエリート軍人だった。戦後、ふるさと玉造町に戻り、分家して玉造の駅前通りの一角に店を構えた。店の仕事は妻のまきさんが支え、忙しいときには青年団の後輩である中田光(みつる)さんが応援に来た。コロを連れてきたのは、その光さんだった。
「まだかな、まだかな。名前はコロだよ」あどけない表情で表通りを見つめる陽子ちゃん、おさげ髪がせわしげに揺れている。お母さんが縫ってくれた水玉のワンピースを着て、コロとの初対面を今か今かと待っていた。「すぐ、来るから、中にいなさい」今にも通りに飛び出しそうな陽子ちやんを母・まきさんは店の中から制した。「ほら、光さんのオート三輪が来たぞ。今角を曲がった!」 荷造りをしていた父・良昌さんも手を止めて立ち上がった。ドッドッドッという地響きのようなエンジン音は、離れていてもすぐ分かった。
外へ出ると、砂煙をあげたオート三輪車が近づいてきた。「わーい、コロが来た」 陽子ちやんは跳び上がって喜んでいた。両親も店頭に出て、コロを出迎えた。小犬は助手席に置かれた竹籠の中で、スヤスヤと眠っていた。垂れた耳、無じやき邪気な口もと、フサフサとした体毛、まるで愛らしいぬいぐるみがそこにあるようだった。
「かわいいー。コロ、コロ」子ちゃんはそっと頭をなでた。コロは目を覚まし、一瞬キョロキョロとした後、少女の頬をペロリと舐めた。「コロのごあいさつね」 まきさんが笑いながら言った。「良いお友達になりそうだ」良昌さんも目を細めた。
「こっこちゃん、コロはボール遊びが大好きなんだ。よく遊んであげるんだよ」光さんはエンジンを切りながらそう言った。「陽子ちゃんは、当時こっこちゃんと呼ばれていました。で、そのこつこちゃんが、犬を飼いたいというんで、小犬を探してきたのです。確かテツという犬の子でした」と光(みつる)さんは当時を回想する。
生後四か月の小犬は茶色い毛の雑種で、人なつっこい性格だったので丸島家な」コロとこっこちゃんと光さんは当時を回想する。
生後四か月の小犬は茶色い毛の雑種で、人なつっこい性格だったので丸島家にすぐに馴れた。コロと名付けられ、さっそく陽子ちゃんの遊び相手になった。
朝起きると裏庭でボール遊びと追いかけっこ、幼稚園から帰ってくると再びボール遊びと散歩。コロとこっこちゃんは、むつまじい兄弟のように時間があればじゃれあった。
「陽子は、石岡の善隣(ぜんりん)幼稚園に鹿島鉄道で通っていました。三つ上の姉・裕子も善隣を卒園しています。裕子のときは玉造から数人通っていましたが、陽子のときは一人でした。商売が軌道に乗り始めたものの、石岡の幼稚園に通わせることは決して楽ではありませんでした」と丸島さんは振り返る。親として子供にきちんとした教育を受けさせたい、その一心で二人の娘を石岡まで通わせた。
「私自身、父親によく言われました。土地や財産を増やすより、教育を身に付けた方が良いと」鹿島鉄道の玉造駅までは二百メートルの道のり。最初のうちは母・まきさんが駅まで送り迎えをした。そのうちにコロがそれに加わり、いつのまにかコロだけが陽子ちゃんの送り迎えをするようになった。
「コローっ、幼稚園へ行くよー」赤いポッケのエプロンを着た陽子ちゃんは、犬小屋に声をかける。コロは尻尾を振って飛び出してくる。「行ってらっしやい!」両親が声を揃えて見送る。
自宅を出て、駅へ向かう通りを並んで楽しそうに歩く。 「コロ、歩くのが速い。靴が脱げちゃうよ」 陽子ちやんが、笑いながら話しかける。コロはそれでもペースを変えずに歩いて行く。「もう、コロは速いんだから」 コロとこっこちやんいて行く。「もう、コロは速いんだから」と言いながらも、笑顔が弾けそうだ。駅までの道のりが楽しくてしょうがないという様子だ。
「あら、こっこちやん、今日もコロがいっしょでいいね。行ってらっしやい!」 近所のおばさんが声をかける。四歳のかわいい女の子が小犬といっしょに商店街を歩いて行く光景は、ほほえましい。コロは駅に着くと、陽子ちゃんといっしょに改札口を通り、ホームで列車を待つ。鉾田方面からの列車が到着すると陽子ちやんと共に乗り込み、頭をなでてもらうとくるりと引き返し、改札口を抜け自宅へ戻っていく。 夕方は、改札口で陽子ちゃんの帰りを待っている。
これがコロの日課だった。「ある日、時間が過ぎても陽子が帰ってこない。どうしたのかなと思っているところへ、鉾田駅から電話がかかってきました。寝過ごして鉾田まで来てしまったので帰りの列車に乗せた。迎えに行ってくださいという親切な連絡でした。さっそく駅へ迎えに行くと、コロがちゃーんと改札口の前で待っている。ああ、なんて忠実な犬だと思いましたよ」と丸島さんは改めて感心した様子で話す。
そのころ、丸島さんの会社は、大忙しの毎日だった。店を手伝っていた光さんは、こう振り返る。「イソライトかまどという新しいかまどを売り始めました。これは薪が三本あればご飯が炊けるという優れたもので、鹿行(ろっこう)地方全域を売り歩きました。とにかく売れるので、忙しかったです」さらに丸島さんを、次のように讃えた。
「先見性のある大先輩でした。陸軍士官学校を出て、終戦でしょう。玉造に帰ってきて、一時期役場の農地委員会で農地改革の仕事をやっていた。土地の権利の問題だから、苦労したと思いますよ。で、その頃青年団のリーダーでした。そこで、いろんなことを教えてもらいました。日本で最も早く青年学級を開いたのも丸島さんです」 先見性と先進性は、仕事でも発揮されていた。時代はかまどからボイラーヘ移り、ボイラーの売り上げが販売店で一番を記録したこともあった。「とにかく忙しかったですよ。夜寝る間もないときがあったほどですから」と丸島さんは懐かしそうに語る。
しかし、どんなに忙しくても丸島さんたちはコロに愛情を注いだ。特に、陽子ちゃんは心からコロをかわいがった。「お座り」「伏せ」と命じると、コロは即座に反応するようになっていた。
犬の年齢を人間にたとえると、次のようになる。
・生後四か月 六歳
・生後一年六か月 二十歳
・以後、一年で四歳加算(注‥犬の種類によって差異がある)これによれば、コロは人間で言えば六歳から二十歳ぐらいまで丸島家で育てられたことになる。
幼児期から成人までの大切な期間である。特に、幼児期は性格形成の基礎となる時期で、このときの躾は一生を左右する。コロは、この大切な時期を丸島家の愛情をたっぷりと受け、すくすくと育っていった。陽子ちゃんが幼稚園の年長クラスに進級した年は、東京オリンピック開催の年だった。1964年10月~
この時期、石岡善隣幼稚園は園児数が急増していた。団塊の世代はすでに中学生になっていたが、好景気の波の中、幼児教育に力を注ぐ家庭が増え、どの幼稚園も園児が増加していた。
とりわけキリスト教系の善隣幼稚園は、先駆的な教育方針が評判を呼び、多くの入園希望者が殺到した。隣接の美野里町や千代田村、さらには鹿島鉄道沿線の玉造町、鉾田町など遠方からも園児が通うようになった。そのピーク時には試験や面接が行われ、幼児がふるいにかけられた。「私は二年保育で入ったのですが、入園児はテストを受けました。教室に入るとテーブルがあり、そこに座るとお菓子がありました。奥山園長先生がすぐ前にいて、私は男の子といっしょでした」と陽子さんは回想する。男の子はお菓子に手を出し、陽子ちやんは遠慮して座ったままだった。
その様子を見た奥山園長は、慎み深い陽子ちゃんを合格とした。ユニークな面接だったが、このテストをパスしたことで陽子ちやんの通園が決まった。「奥山先生から、いろいろな言葉を教わりました。今でも覚えているのはこの言葉です。『己の心を修めるは、城を攻め取るにまさる。』これを何度も復誦しました。幼稚園児には難しすぎる言葉ですよね。意味が分かったのは、大人になってからでした」
これは旧約聖書の「箴言(しんげん)」にある格言で、全文は次のようになる。
「怒りをおそくする者は 勇士にまさり
自分の心を修める者は 城を攻め取る者にまさる」
ここでいう勇士は、城を攻め取るほどの勇気と武力を持った優れた人である。真の勇者とは、自分の心を修める人だと言うのである。 日本にもこれと似た言葉がある。「山中の賊を破るは易く、心中の賊を破るは難し」陽明学の言葉として有名だが、いつの時代でも自分の心を律することが大きな課題になっている。
幼児に普遍的な言葉の種をまいてそれが大人になって開花するという、教育のお手本のようなケースだった。ともあれ陽子ちやんは、日ごとに幼稚園生活に慣れ、楽しい列車通園が続いた。もちろん、コロの日課である駅への送迎も順調だった。商店街の人たちばかりでなく駅員さんとも顔見知りになり、ちょっとしたまちの人気者になっていた。
東京オリンピックが幕を閉じ秋が深まるころ、コロにとって大きな転機が訪れようとしていた。それは、穏やかな晩秋の朝のことだった。いつものように歩く陽子ちゃんとコロの目の前に、大きな荷物を担いだ年配女性がいた。彼女は改札口を過ぎてホームに着くと、足元にドカッと荷物を置いた。その荷物は大きく、ホームの中でもひときわ存在感があった。当時、この地方では霞ケ浦の水産物や農産物を売り歩く行商の女性が多数いた。自分の体重ぐらいある商品を背負いカゴに詰め込み、その巨大な荷物を担いで列車に乗り込む毎日だった。「行商のおばちゃん」と親しまれ、都市部へ出て商いをして歩いた。ウナギやワカサギ、エビ、ゴロの佃煮のほか、新鮮な野菜と餅など季節の食材が手に入るため、家庭の主婦は歓迎した。
東京へ向かう常磐線の列車では行商専用の車両があって、そこに女性たちが乗り東京・千葉方面へ向かうのである。
鹿島鉄道を利用する行商の女性たちは、小川町や石岡市などの人口が密集する地域を歩き、生産物を提供していた。戦後から昭和未までよく見かけたまちの風物詩でもあった。
列車が到着し、陽子ちゃんとコロが乗り込んだ後、その女性はドアの前に荷物を置き、そのそばに立っていた。いつになく車内が混んでいる日だった。 コロが頭をなでられて列車を降りようとしたとき、大きな荷物がその行方をさえぎった。コロは前に進むことができない。
そのうちにドアが閉められ、列車はゴトンゴトンと動き出した。仕方なくコロは、陽子ちやんの座席まで戻って足元に座った。「あれ、コロどうしたの?」驚いた声を上げ、コロの体をなでてあげた。
陽子ちゃんの顔を見て、コロは安心したのか足元で眠り始めた。車窓から見える霞ケ浦のさざ波を見て、陽子ちゃんは次第に不安になっていった。
「石岡駅に着いたら、車掌さんに頼んで、お家に電話をかけてもらおう」そう考えるとちょっぴり安心できた。常陸小川駅から、しかむら駅、新高浜駅とだんだん石岡駅に近づいてきた。「石岡、石岡」ホームでアナウンスが響いていた。同時に、車掌が列車内を歩いてきた。通勤通学の人たちがぞろぞろ降りていく。車掌さんに電話のことをお願いしよう、そう思うと胸がどきどきした。
「あれ、この犬はお嬢ちゃんの犬かな」改札口で駅員がコロを見つけ聞いてきた。「………」陽子ちゃんは言葉に詰まった。言おうとする前に質問され、どう答えていいか分からなくなってしまった。コロは切符を持っていない。それなのに乗ってきたのだから、悪いことをしているんだ。
そう思うと、もう何も言えなかった。「お嬢ちゃんの犬なの!」 今度は強い語調で言ってきた。陽子ちやんは何も言えず、首を横に振った。「そうか、そんなら出て行ってもらわなくちゃ。ほらワン公、外へ出ろ!」 そう言って駅員はコロの尻を叩いた。コロは驚いて飛びあがり、ホームを逃げるように走り、やがて線路に降り駆け出して行った。
「コロ、コロー」

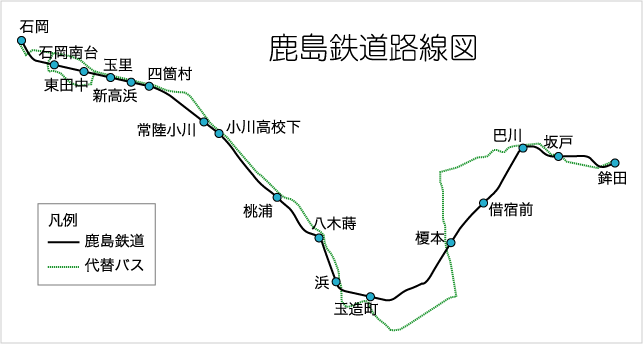



.png)
.png)