 ■出雲の謎を解く
■出雲の謎を解く

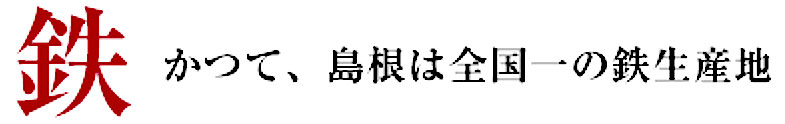


 つまり、出雲氏の本拠地意宇部の中の神聖な地とされたところで、玉作りが行なわれたのである。しかも6世紀末以降にあっては、出雲の忌部の神戸(かんべ)以外の地で玉作りが行なわれた形跡はない。各地の玉作りに関する遺跡が、その時期に妄に姿を消すのである。6世紀は、高天原神話の確立に力を入れた欽明天皇のあとをうけた敏達天皇の治世にほぼ相当する。敏達天皇のときに、朝廷の祭祀には必ず出雲の玉を用いよという命令が出されたのであろう。そのことは、朝廷がかつて銅剣・銅矛の有力な生産地であり大国主命信仰を生み出した出雲を重んじていたことを物語る。
つまり、出雲氏の本拠地意宇部の中の神聖な地とされたところで、玉作りが行なわれたのである。しかも6世紀末以降にあっては、出雲の忌部の神戸(かんべ)以外の地で玉作りが行なわれた形跡はない。各地の玉作りに関する遺跡が、その時期に妄に姿を消すのである。6世紀は、高天原神話の確立に力を入れた欽明天皇のあとをうけた敏達天皇の治世にほぼ相当する。敏達天皇のときに、朝廷の祭祀には必ず出雲の玉を用いよという命令が出されたのであろう。そのことは、朝廷がかつて銅剣・銅矛の有力な生産地であり大国主命信仰を生み出した出雲を重んじていたことを物語る。