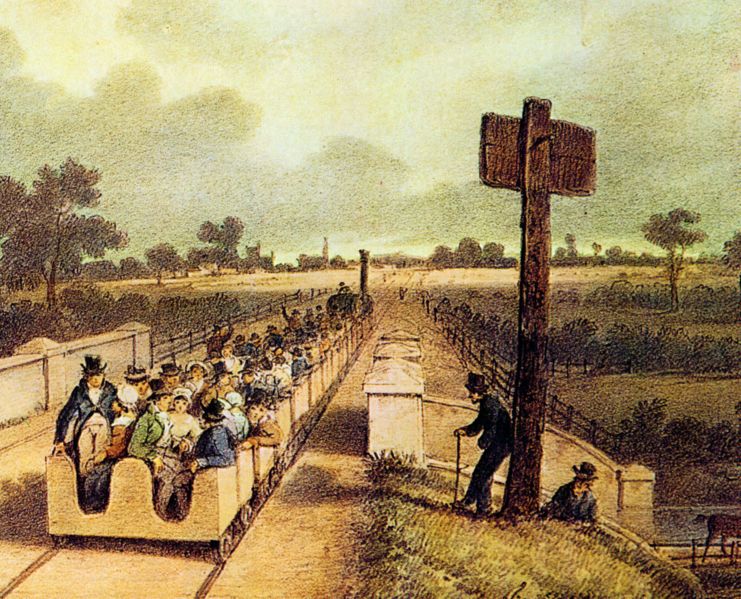■ポロネーズ
■ポロネーズ
▶︎ショパンの男性的な面があらわれたジャンル
ポロネーズもポーランドの民族舞曲のひとつですが、こちらは宮廷まで広がった踊りですね。もともとメヌエットのような音楽で、その起源は16世紀頃にまでさかのぼることができます。18世紀にはバッハやテレマン、モーツァルトらがポロネーズのリズムを取り入れた音楽を書いていましたが、ポーランドの作曲家たちもポロネーズを作曲するようになります。(ポーランドを分割占領した)
ロシアに対する抗議の意味合いもあったのでしょう。19世紀初頭になるとポロネーズは愛国的な音楽として人気のあるジャンルになります。
ショパンの最初の作品は7歳のときに書いた「二つのポロネーズ」(1817年作曲) ですが(ちなみに、最後の作品は1848〜49年に書かれた「マズルカ」ヘ短調 作品 68-4)、ショパンのポロネーズについて話す前に、一人の重要な人物について述べておきたいと思います。ミハウ・クレオファス・オギンスキというポーランド貴族。作曲家でもあり、外交官でもありました。彼の作曲したポロネーズはとてもポピュラー(ロシアでは大勢が口ずさむほど!)になりましたが、ショパンに少なからず影響を与えたと思われます。
オギンスキのポロネーズの特徴は、一般的に言えば、とても抒情的でメロディアスであり、メランコリーにあふれていることです。もちろん、「タン・タタタン・タン・タン・タン」というポロネーズ独特のリズムも出てきます。
オギンスキのポロネーズは、単なる舞曲ではなく、さまざま気分の変化を伴った、「詩」曲のよう音楽といえるでしょう。ある意味、舞曲から逸脱しています。少年時代のショパンは、このオギンスキのポロネーズの流れを受け継ぎました。ショパンのポロネーズもまた、詩のようであり、英雄的で洗練されています。ポーランドの偉大な過去をうたう気高いポエム、という趣です。ポロネーズにおけるショパンの終着点が「ファンタジー(幻想曲)」になったのは象徴的だと思います。最後のポロネーズ「Polonaise-Fantaisie(幻想ポロネーズ)」作品61は、ポロネーズを使った詩情あふれる幻想曲です。
ポロネーズはショパンの創作のうえで、男性的な面が非常に強くあらわれているジャンルです。何度も言うように、ショパンには「女性的」で「やわらかい」というイメージがぁりますが、人間としては非常に強い心(魂)の持ち主だったと思います。たしかにショパンの音楽は抒情的で詩的です。でも、その詩情は男性的なもので、基本の部分でしっかりしており、強靭です。ショパンの音楽は弱々しい嘆きや訴えのようなものではありません。その音楽を聴けば、ショパンがどれほど自分自身のことや自分の哀しみについて知っているかが分かる。現実をはっきり見る力がとても強い人だったと思います。自分がどうなっているか、自分の周りで何が起こつているか、それがはっきり見える人。ポロネーズにはそのようショパンの精神的な力強さがあらわれています。
このことに関連があるかもしれませんが、ショパンは非常に鋭いアイロニーの持ち主でした。人を真似て周囲を笑わせる才能があったと言われています。ある有名な当時の役者がショパンを見て、音楽家にならずに役者になればよかったのに……、と述べたというエピソードが残っているほどです。

▶︎悲劇的でドラマティック
ショパンのポロネーズは、子ども時代の作品を除くと全部で7曲あります。全体的に暗くて悲劇的な感じの音楽です。マズルカと同じように、3/4拍子。そして、「タン・タタタン・タン・タン・タン」という独特のリズムが繰り返されます。ショパンの魂の詩情、しかも悲劇的な詩情をあらわしているのもマズルカと共通しています。 ピアニスティックな調性で善かれた第3番「軍隊」(イ長調)と第6番「英雄」(変イ長調)、
この二曲だけは明るい曲想で、賛歌的な性格をもっています。あと第7番(「幻想的ポロネーズ=変イ長調)を除くと、他はそれぞれ暗い調性(第1番卜嬰ハ短調、第2番=変ホ短調、第4番=ハ短調、第5番=嬰ヘ短調)で、ソナタ第2番のような悲劇的なキャラクターが強い。
晩年に近づけば近づくほど、ポロネーズはより洗練され、より強烈でドラマティックになります。形式のうえでも、表現のうえでも、よりコントロールされたものになっていく。語りのような、レチタティーヴォ(朗誦・ろうしょう・詩句などを大きな声を出して読むこと)の要素が増えていくのも特徴的で、第5番はその頂点にあたると思います。この曲についてショパンはウィーンの出版商メケソティに宛てた嘉の中で次のように書いています。「今そちらにお渡しできる手書きの楽譜で、ポロネーズの形式で書いた一種の幻想曲がありますが、自分としては「ポロネーズ』と名付けるつもりです」(1841年8月23日付)。この曲の中間部に「マズルカのテンポで(Tempo di Mazuruka)」という指示が与えられているのも興味深い点です(譜例8 – 1)。
ポロネーズにおける曲想指示について、ショパンが「Maestoso(堂々と)」という言葉にこだわるのも、とても面白いですね。七曲のポロネーズのうち、四曲の冒頭で使われています。それ以外に「appassionato(情熱的に)」「Con brio(輝かしさをもって)」といった指示が目を引きます。いずれにしても、ポロネーズが、テンションの高い、「グランドスタイル」の音楽であることの証拠でしょう。第5番だけはテンポ指示がありませんが、それはショパンの実験的マインドのあらわれではないかと思います。手紙の中にもあった「一種の幻想曲」という概念は、後の「幻想ポロネーズ」の中でもっと意識的に扱われるようになります。ショパンの全作品のうちでももっともむずかしく、美しく、特別な作品と言われるのが、この「幻想曲ポロネーズ」です。
ポロネーズの中では壮麗なテクニック・・・オクターヴや和音の連打など・・・が使われています。マッシヴ(力強く)でダイナミックスも幅広い(ffだけでなく、第2番ではfffまで出てくる!)。演奏するためにはとてつもないエネルギーと体力を必要とします。ショパンは晩年、自身の演奏会のプログラムからポロネーズを外すようになりますが、やはり体力的にむずかしかったんだろうと思います。
▶︎ 第6番変イ長調作品53「英雄」
もっとも華やかなポロネーズで、とても人気のある作品です。この曲で注目すべきは冒頭の曲想指示です。たった一言「マエストーソ(堂々と)」。深い意味を持った、演奏者に対する重要なメッセージだと思います。ショパンはこの曲が速いテンポでやかましく演奏されることを非常に嫌がっていたそうです。ヴィルトゥオジティ (名技性)や輝かしさといった、この作品の演奏のうえで見せなければならない要素と、気高い精神性や品格など、まさに「マエストーソ」の指示が要求する要素との間で、バランスを取るのがむずかしいところです。
形式のうえでは、第5番のスケールの大きさを引き継いだような作品で、独創的な中間部を持っています。第5番の中間部はマズルカの要素を持つ音楽でしたが、この第6番の中間部は左手のオククーヴの連続によるヴィルトゥオジティ(名技性)が非常に印象的です。
メイン主題(譜例8 – 2、小節17〜)では、ショパンの細かい指示に注意したいと思います。この主題、とてもシンプルなメロディですね。音域は狭いし、ある意味でショパンらしくないと言えるかもしれませんが、単純に見える左手のリズムは、簡単ではありません。スラーとスタッカートを使って、ポリフォニック(複数の独立した声部(パート)からなる音楽のこと)なつくりになっている。さらにディミヌエンド(だんだん弱く)の指示。ショパンはディミヌエンドにかなりこだわっていると思います。この指示を守るかどうかで、曲のキャラクターが大きく変わります。主題が出てくるたびにショパンはディミヌエンド記号を書いていますが、このこだわりは大事にしたい(ちなみに、一カ所だけ、小節65には指示がないことにも注意すべき)。
小節26(譜例8 – 3)も細かいです。3拍めの裏、左手は8分音符ですが、その上の右手には32分休符が書かれてある。左右両方を正確に見せるのは簡単ではありません。とにかくすべてが細かく書かれているわけですが、こういったディテール(全体の中の細かい部分)を実現することが演奏のうえで重要だと思います。
でも、このポロネーズのいちばんユニークな部分はやはり中間部でしょう。ちょっとリストっぽいというか、ショパンにしては珍しく直接的にヴィルトゥオジティ(名技性)を前面に出している箇所(譜例8 – 4、小節83 ~)。この左手のオクターヴの連続は、バレエにおける32回転を連想させます。バレエの場合、回転の途中で倒れないように気をつけるわけですが、ピアノの場合は、回転の中心軸にあたるものを左手の中に見つけることが大切です。小節121〜128(譜例 8 − 5)は、そんなふうには見えないかもしれませんが、むずかしい箇所のひとつです。構造のうえでも大事な箇所。前の(オクターヴが連続する)部分のテンションをキープしながらも和らげるところで、高貴さと品格を持って、ポリフォニックに演奏しなければなりません。小節125はベースを、小節126〜128は内声部をうまく見せたい。それから、小節126~128のペダルの使い方にも注意します。
小節129からの抒情的でポエティックな部分(エピソード)は、曲全体に対して大きなコントラストを作っていますが、ペダルの使い方で繊細な色合いを表現したいところです。小節147〜150(譜例8 – 6)は、ベースに付けられたスフォルツァート(ある音符または和音に強いアクセントを与えること・sfあるいはsfzと略記)と、右手のメロディの中で何度も繰り返される「ド」に付けられたアクセントを大切に。小節147〜150、「Smorzando(消え入るように)」はメロディとハーモニーがレース生地のように織り合わされ、奇跡的な美しさを生み出しています。
この詩的なエピソードのあとにポロネーズ主部が戻ってきますが、ここでポロネーズはより複雑に、本当の意味での「マエストーソ(堂々と)」な性格で響きます。華麗なコーダでも、ショパンはディミヌエンドにこだわっています。小節176〜178(譜例8 – 7)にはディミヌエンド記号をいくつも書いている。最後の最後で、ようやく華やかな解放感をもって曲が閉じられますが、小節178の左手のオクターヴは中間部の思い出みたいなものでしょうか。
▶︎ 第7蕃変イ長調作品61「幻想ポロネーズ」
ショパンの全作品の中でも独特な位置を占める一曲です。他のどの作品とも、もちろんどのポロネーズとも異なっていて、ショパン晩年を代表する特別な傑作と言えるでしょぅ。ショパンにとっての「最後の告白」であり、「白鳥の歌」です。この曲の内容を語るのは本当にむずかしいですね。自分自身が詩人にならなければ語ることができないほど、内容が豊かです。


ところで、詩人について。私の大好きなロシアの詩人でヨシフ・ブロツキーという人がいるのですが、彼は次のように言っています1・「いかなる言葉も、詩人にとっては、終わり(終着)ではなく、思考の始まりにすぎない」。つまり、言葉を口にする詩人は、次の段階へ進み、韻を選ぼなければならない。詩人は言葉の生命を延長するのだ、とブロツキーは言うんですね。これは、まさに「幻想ポロネーズ」の中で起こっていることだと私は思います。
初の二つの和音から、すでに詩そのもの、という段階にあります。絶対的な詩です。最初の和音は変イ短調(as-moll)。この曲のメインの調性である変イ長調(As-dur)の同主調です。ショパンの手は、次の和音として変ハ長調(Ces-dur)を生み出します。詩における「韻」ともいうべきこの短3度「変イ(ラ♭)」〜「変ハ(ド♭)」は、曲全体の調性関係における核となります。続く小節2や小節7〜8でも、この短3度の「韻」が使われます。この序奏の部分、ショパンはまったく自由に振る舞っています。ひとつひとつの和音とそれに続くパッセージのなかで、私たちが聞くのは詩人ショパンの声のテンション(強弱・抑揚)であり、その声に導かれるように、音楽の進行とともに、私たちは現実世界を超えた別世界を体験することになるんです。(譜例8-8、小節1〜8)。
曲の中間部(譜例8−9、小節148~)はロ長調ですが、これもたいへん重要。「ロ(シ)」は先ほどの「変ハ(ド♭)」の異名同音なんですね。つまり、「変ハ長調(Ces・dur)」=「ロ長調(H-dur)です。ロ長調というのは、ショパンにとって特別な調性でしたが(ソナタ第3番の第3楽章や、「幻想曲 作品49」のコラールの部分、あるいはスケルツォ第1番の中間部などを思い出してください)、この曲の中でも特別意味合いを持っています。
ロ長調のセクションは、曲全体にとっての中間部と同時に、ソナタ形式における第2主題にもあたります。この曲の肝というべき箇所。異次元の世界、あの世への展開です。
音楽は小節148〜のコラールを経て、ノクターン風の部分(小節152〜)へ転じます。メロディとハーモニーが一体となった、左右の手が分けられない世界。昼と夜が出会う場所です。夜に真っ黒な太陽が輝いているかのよう! この曲の中でもっともポリフォニックな箇所だと思います。
その後、問いかけのよう至一つの和音(譜例8 – 10、小節180)に続いて、ショパンの書いた音楽のうちでもっとも親密なべージがきます。私の大好きな箇所です。レチタティーヴォ(小節望に続く美しいメロディは、嬰ト短調(gis-moll)ですが、これはロ長調(H – dur)の平行詞ですね。また、言うまでもなく「嬰ト」は「変イ」の異名同音です。これほど哀しく、感動的な音楽もありません。詩人が自分自身に語りかけるよう言葉ひとつひとつが、もっとも抒情的で親密な情感を持って響きます。と同時に、なにかひとつの決断・・・厳しい覚悟、死に向かうような覚悟がなされる箇所だと私には感じられます。演奏のうえでは、抒情的なものと、ストイックな覚悟を同時に見せるのがむずかしいところです。荘厳な精神性をもって、男性的で揺るぎない決意がなされる。そういう細やかな心の動きの表現はまったく見事としか言いようありません! 上下行する一音一音が私たちの心に突き刺さります。
そして、すべてがストップする瞬間が訪れます。時間すら消えてしまう。小節199〜(譜例8・11)、静けさの中からトリルが生まれます。もっともミステリアスで天才的なトリル。このようなトリルは他に例を見ません、と言いたいところですが、私はベートーヴェンの晩年のソナタに出てくるトリルを連想します。あるいはシューベルト最後のソナタの第1楽章に出てくる不気味なトリル。同じ「人生の真実」が表現されているということでしょうか。ここでは、突然すべての事柄を理解し、すべてを抱擁するような、「悟り」のような瞬間が生み出されます。ロシアの詩人、マリナ・ツヴエターエワの詩の一節を思い出します。「空の真実の声/この世の真実の声に反して」。ここは、ベートーヴェン晩年の作品のように、人間の尊厳や偉大さの頂点にあると思います。「Sursum Corda(心を高めよ)」ですね。でも、同時に、モーツアルト的を明噺さ、シンプルさ、純粋な古典的精神でもある。本当にこの世を超えた世界であることは間違いない。ピアノの詩人が「永遠」と「tete-a-tete(顔と顔を合わせて)」で向き合っています。
再現部とコーダもひじょうに独特です。最後の数ページに関して、ゲンリヒ・ネイガウスは「精神を高めて」と書いています。ポーランドのエピックな精神の高まりを表現したいところです。小節238〜241(譜例8 – 12)、バラード第1番と同じやり方で、「半音・全音・半音・全音」の並びが重要な転換を告げます。ダイナミクスも拡大します。「f」→「forte assai」(きわめてフォルテで)」→「piu forte(もっとフォルテで)」→「ff(フォルティッシモで)」→「Sempre ff (ずっとフォルティッシモで)」。その頂点で、中間部のメイン主題がポロネーズを思わせるリズムで、輝かしくマエストーソな感じであらわれます(譜例8 – 13、小節254~)。初めて出たとき(小節152〜)とはまったく異なったキャラクターになっています。ここはクレッシュンドとディミヌエンドの指示を大切に弾きたいですね。小節260と262の左手、16分休符があります。細かいですが、これもきちんと見せたい(譜例8 – 13)。
最後の部分もミステリアスです(語例8 – 14)。全体がディミヌエンドしていき、小節282でpp(ピアニッシモ)。左手にトリルが出ますが、ここはテンションを保つのがむずかしいところ。小節287の3拍目、休符に付けられたフェルマータにも注目です。最後の2小節はペダルを踏んだままをのですが、休符の長さの加減がむずかしい。同じくフェルマータの付いた最後の和音、輝かしいガですが、私にとってはなにかショパンの無念さのようなものが感じられて、決して「万歳」ではないと思います。謎につつまれたエンディングです。本当にすべてがむずかしい作品です。内容もさることながら、サウンドに関しても。バラードと同じように、さまざま声部が絡み合っていて、声の魅力を出さなければならないうえに、歌と語りのバランスも重要です。リズムも簡単ではありません。曲の構造も複雑です。ソナタ形式に対するショパンの憧れなのでしょうか、ソナタ形式の要素を意識的に使っていると思います。その一方で即興的な要素もあって、一筋縄ではいきません。「頭」と「心」のバランスを取るのがむずかしい、まったくすごい作品です!
▶︎おすすめの演奏
「英雄ポロネーズ」では三人の演奏をおすすめします。まずは、オイケン・ダルベール。古い録音なので音質は正直よくないです。しかも、短縮版。それでも、あえて推薦したくなる素晴らしい名演です。テンポ感、マエストーソ感、ポロネーズらしいリズム感。厳しさと自由さの組み合わせ。とにかくハーモニーを注意深く聞きながら全体をコントロールしている。ポロネーズ主題が最後に再現される前の抒情的をエピソードは、とてもさっぱりした、やや急いでいるような感じですが、SPレコードの収録時間の関係だったのかもしれません(笑)。短縮版でをいフル・バージョンでぜひ聴いてみたかったです。
二人目はウラディーミル・ホロヴィツツ。この曲はホロヴイッツの18番ですね。マエストーソ(「荘厳な」または「堂々とした」)だけでなく、軽さの感じが素晴らしい。ダイナミックスの使い方がとても上手です。ピアニスティックな観点でも余裕たっぷりで、聴きどたえ十分です(1971年のスタジオ録音)。
ヨ−ゼフ・レヴイン。一言でいえば「完璧」な演奏。ブリリアント、ヴイルトウォーゾ。こういう演奏を聴くと背筋が伸びます(笑)。和音の中でこれほどのポリプオニー感を出せるというのは奇跡的。造形もきちんとしていますが、硬すぎず、自由さもある。マエストーソ感も申し分ありません。
「幻想ポロネーズ」はスヴヤトスラフ・リヒテルの演奏がおすすめ(1972年プラハでのライヴ録音)。私にとってベストともいうべき演奏です。弾き手の姿が消えて、のによる語りになっているのが素晴らしい。清澄なハーモニーが歌っています。の見せ方も見事。そして、師匠ネイガウスの魂を受け継いだよう皇日の美しさ。 プラハで音そのも曲の構造ユなんといぅ音でしょう。音の中にある静けさが素晴らしく、過去への思いや、未来への思いが、ひとつひとつの音、現在という瞬間に立ち上がります。
ゲンリヒ・ネイガウスによる1958年のライヴ録音。演奏者が「詩人」となって作品のエッセンスを見事に引き出しています。コンサートの実況録音で、緊張のあまり、ところどころ弾き間違えるのですが、ミスタッチにすら味があります。芸術家の魂、パッションがより強く伝わってきます。
アルフレッド・コルトー。パッションに満ちた演奏で、ショパン晩年の作品にしては元気すぎ、熱すぎる感じがしなくもありません。「幻想ポロネーズ」というよりも「熱情ポロネーズ」みたいな感じ(笑)。でもやっぱり格好いいんですね。音自体(音の分厚さ、深さ、音のもつポエジー)のすごさに感動します。
アルトゥール・ルービンシュタイン。ストイックで落ち着いた演奏です。ひとつひとつの音に重みがあって、マエストーソ感もじゅうぶん。ハーモニーが語っている感じがします。ペダルの使い方も印象的で、ロ長調のコラールのセクションなど、とても透明で美しい。ベースライン(左手)がしっかりしているので、その上に乗るハーモニーが本当にきれいに聞こえるんですね。音が立って聞こえます。クライマックスでの盛り上がりも、ブリリアントでヴイルトウォーゾですが、表面的でなく、品格がある。昔の高貴な騎士のようなイメージです。
ルービンシュタインにはポロネーズの全曲録音がありますが、とてもオーセンティック(本物の,確実な,真正なという意味)で立派。おすすめです。
最後に、ウラジーミル・ソフロニッキーによるポロネーズ第1番を挙げておきます。素晴らしい演奏です。叙事的ともいうべき、2大なスケール感。ひとつひとつの音に込められた情念の深さにはただただ圧倒されます。悲劇的なヒロイズムの表出においては、ソフロニッキーの右に出るピアニストはいないと思います。絶対に忘れられない名演のひとつです。
■ショパンの生涯 略年表
▶︎ワルシャワでの幼少期
1810年 – 0歳:ワルシャワ公国中央のジェラゾヴァ・ヴォーラに生まれる。
1816年 – 4歳:姉ルドヴィカにピアノを習い始める。
1816年 – 6歳:アダルベルト・ジヴニーのもとで本格的にピアノの指導を受ける。
1817年 – 7歳:最初の作品『ポロネーズ ト短調』を作曲・出版。
11818年 – 8歳:ワルシャワではじめて公開演奏。曲目はギロヴェッツの『ピアノ協奏曲』。
11821年 – 11歳:ピアノのテクニックは向上し,既にジヴニーの指導するところではなくなる。また作曲に対する興味が強くなる。
11823年 – 13歳:エルスナーより対位法・和声学を学ぶ。オペラを好むようになる。
11824年 – 14歳:夏休みを利用し国内旅行。ポーランドの田園に親しむ。ポーランドの民族音楽に触れ,強い関心を抱く。
11825年 – 15歳:この年作曲したロンドに初めて作品番号をつけ,Op.1として出版する。