クラッシックでわかる音楽史
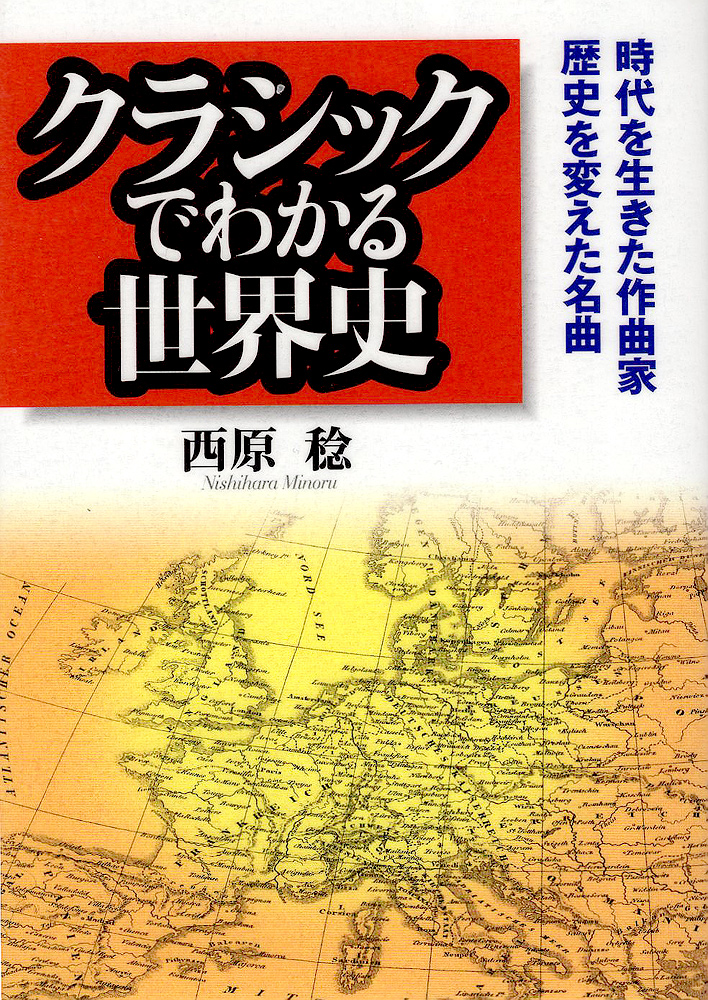 ■はじめに
■はじめに
西原 稔
音楽の歴史はまぎれもなく、世界史の一部である。政治や経済、宗教という大きな問題だけではなく、人びとの日々の生活を織りなす習慣や流行などがひとつの全体となって社会を形成しているのだろう。音楽家もこの社会や世の中のさまぎまな動向や傾向、事件や変動から超然としていることはできないし、生みだされた作品もまた、この世界の動きとつねにどこかで関連している。
音楽や作品の様式は、世の中の実の規範を反映しているが、その美の規範そのものはそれぞれの社会や時代の要求や状況などと無関係ではないだろう。そこに政治や経済的な要素が強く加わるとき、その社会や時代の要求はもっと劇的に芸術活動に影響をおよぼすことになる。
社会の富がどこに集中し、そしてその冨がどのような目的と方針のもとに再分配され、支出されるかという問題と、音楽の活動は無関係ではありえない。たとえば、ベートーヴェンの時代のヴイーンを例にとると、なぜボヘミアやハンガリーの貴族がベートーヴェンのパトロンとなり、ハブスブルク家の皇帝はパトロンとはなりえなかったのだろうか。また、なぜ一八二〇年を過ぎるとベートーヴェンは、その作品をゆだねる出版社をオーストリアからドイツへと移したのだろうか。
この富の集中はさまざまな時代についてとりあげられる問題である。一九世紀になって市民社会が広まってくると、特定の個人への富の集中ではなく、一般に中産階級とよばれる人びとに富が拡散するようになる。そうすると、多少の富をもつ不特定多数の聴衆にどのような音楽を提供すべきかという新たな問題が発生する。そして音楽作品はつねに流行という要因に左右されることになる。流行文化の社会になると、生みだされてくる音楽の種類と質もおのずと変質し、消費に適した音楽が生産される構造になっていく。本書では、名作といわれる音楽作品を象徴的な事例としてとりあげて、それが社会のダイナミズムとどのように関係して生みだされたのかをとりあげる。音楽家と音楽作品は世界史のいとなみの一角をなすという観点にたち、世界史の大きなできごとの側から音楽をとらえなおしてみたいと考えている。
本書が対象としている時代は1550年から1920年までである。すなわちプロテスタント・ルター派の登場によって、ヨーロッパ大陸に宗教と国家の新しい枠組の基盤があたえられた16世紀中頃から、第一次世界大戦終結によって、19世紀近代が終焉をむかえた時期までということになる。一般的な音楽史書によくある中世やルネサンスから現代までの通史ではなく、あえてこの時代枠に限定したのは、ヨーロッパ近代が形成され、そしてその価値観が解体するまでのひとつの大きな流れのなかで、音楽とヨーロッパの歴史をとらえるためである。また、時代区分は音楽史のそれを土台にして、そこに世界史のできごとを重ねあわせている。
▶︎第1章「宗教改革と宗教戦争の時代(1550~1650)
バロック時代前期を対象とし、宗教改革や宗教戦争の記憶が音楽作品にどのように反映したのか、また三十年戦争が音楽作品にどのように投影されているのかをあつかう。
▶︎第2章「宮廷文化と絶対王政(1650~1730)
バロック時代後期にあたるオーストリア・ブスブルク家の結婚政策とフランス・ブルボン家における絶対王政が音楽活動とどのように結びついたのかをとりあげてみる。
第3章「バッハの作品に隠された世界史」
彼のふたつの作品を例に、当時の政治、宗教などの問題とそれらの作品とがどのように関連をもっていたのかを明らかにする。
第4章「揺らぐ宮廷支配」(1730~1790)
音楽史でいう前古典派および古典派の時代をぁつかう。この時代は華美な宮廷文化が、とくにドイツではフランスよりも遅れて栄えるが、同時に、啓蒙主義の思潮の影響や、財政的な披綻、あいつぐ継承戦争などによって宮廷文化が揺らいでいった時代でもあった。こうした視点から音楽をみた場合、音楽史からみるのとは異なる映像が映しだされる。
第5章「モーツアルトの作品に隠された世界史」
この作曲家のいくつかの作品を題材に、彼が生きた時代の側からこれらの作品をとらえなおしてみる。
第6章「フランス革命からヴイーン体制へ[1790~1830]」
初期ロマン主義の時代にあたる。イエーナでノヴァーリスやシュレーゲル兄弟らがロマン主義文学の運動を開始したころ、パリでは革命に続いてナポレオンが擡頭(たいとう)していた。この初期ロマン主義が終焉をむかえるのはヴイーン会議の時期である。それを象徴するのが、フリードリヒ・シュレーゲルがメッテルニヒの政治顧問に就任したことであった。この章ではフランス革命の時期とヴィーン会議の時期の音楽をこの時代のできごとを考える。
第7章「ベートーヴェンの作品に隠された世界史」
ベートーヴェンの作品が当時のヴィーン社会とどのように関連していたのかをみる
第8章「一八三〇年七月革命と音楽」
パリ七月革命とポーランド十一月蜂起を中心にとりあげる。一八三〇年前後は音楽史においても大きな時代の分岐点にあたっている。ベートーヴェンやシューベルトがあいついで亡くなり、代わってシューマンやべ〜リオーズ、リスト、ショパンらが登場し、新ロマン主義の時代ともいわれた。同時にロッシーニがオペラ創作の筆を折ったのもこの時期である。
第9章「ヴィーン体制の終声」
ヴィーン体制の解体という大きなできごとが音楽に何をもたらしたのかを考える。この事件はそれまでの国際体制の解体だけではなく、オーストリア支配下にあった周辺諸国の独立運動を惹起し、そしてその運動に音楽家も参画していった。さらにこの革命はじやつきその翌年のドレスデン革命を誘発していくのである。
第10章「ユダヤ人都市ベルリン」
宗教や政治などの理由による移民と亡命を受けいれたベルリンをテーマに、プロイセンの宗教政策と移民政策が音楽活動にどのように影響をおよぼしたのかをとりあげる。
第11章「ヨーロッパ再編の時代 1850~1890」
後期ロマン派の時代をあつかう この時代は第一回ロンドン万国博覧会からビスマルク宰相辞任までにあたるが、ドイツがたびかさなる戦争によってドイツ帝国を形成していった時代でもある。
第12章「黄昏ゆくヨーロッパ[1890~1914]」
世紀末から第妄世界大戦終結までの時たそがれ期をあつかう。ここではとくにロシア革命と第一次世界大戦において音楽家がどのようにふるまったのかをとりあげる。
第13章「第一次世界大戦と音楽「1914~1920]」
この国際戦争のなかで、フランス、ドイツ、ポーランドなどの国の音楽家が、この戦争とどのように向かいあっていったかを扱う
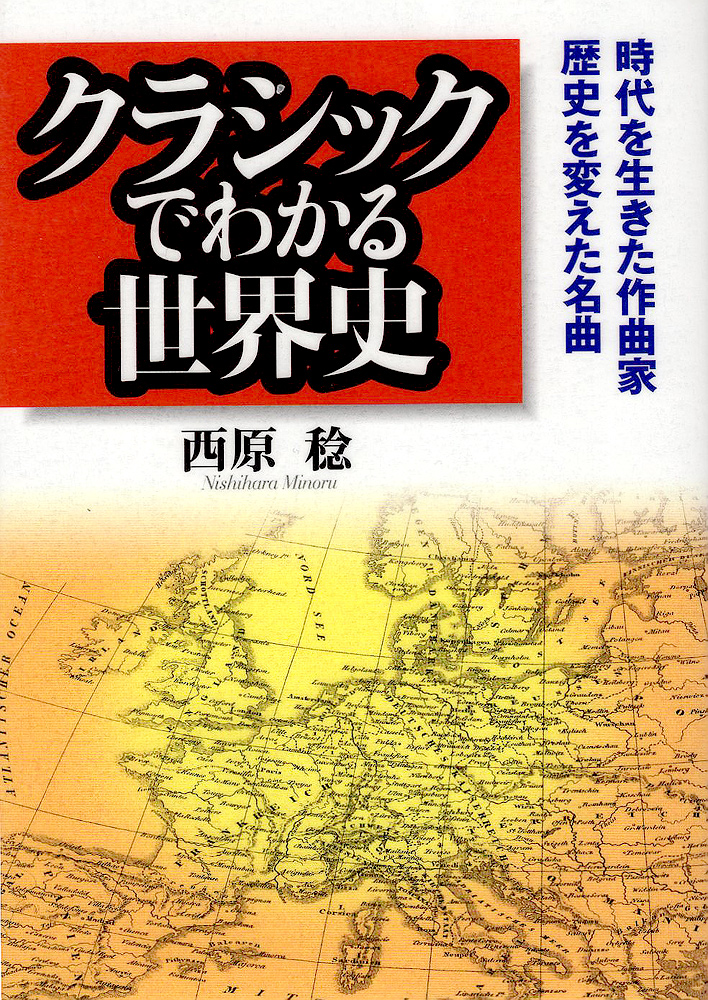 ■はじめに
■はじめに