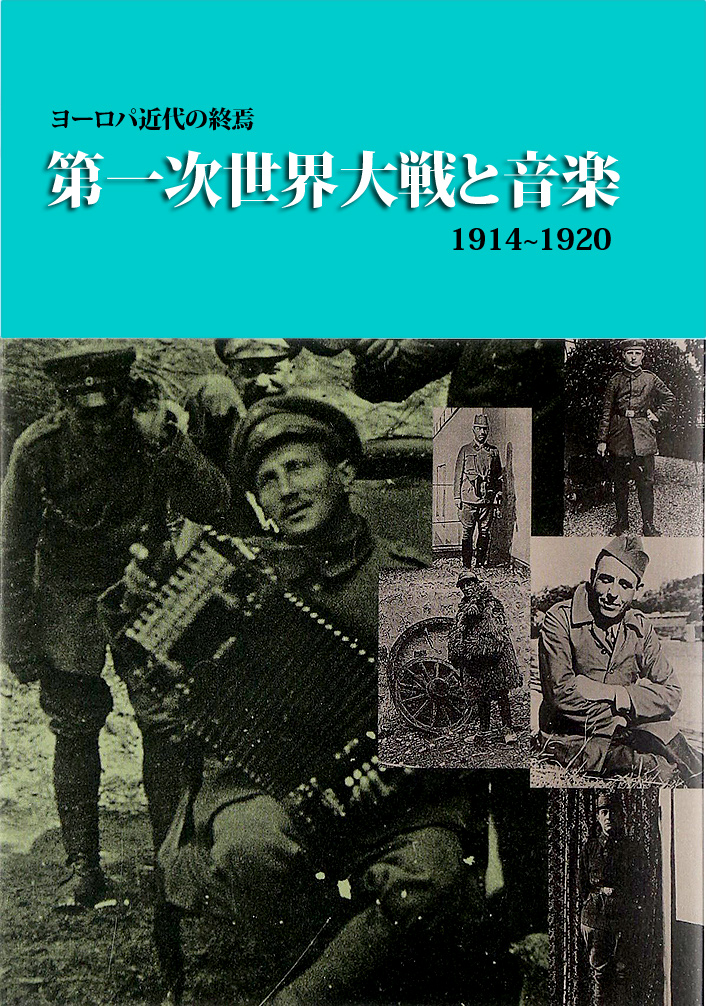 ■第一次世界大戦下における音楽の諸相
■第一次世界大戦下における音楽の諸相
▶︎クルシェネク《ジョニーは演奏する》・・・新ロマン主義の音楽とジャズの鳴り響く
ドイツ20世紀初期のドイツは、黄昏ゆく19世紀と迫りくるモダニズムや異国趣味のはぎまにあった。そのなかにおいていくつかの象徴的な運動がみられた。そのひとつが「青年運動」である。ドイツの大地と過去にたいするロマン主義的なセンティメントを含んだこの運動は、一九世紀の老成した文化に代わって、若者文化を標榜し、ドイツ各地の遍歴をとおして大地と故郷にたいする強い一体性を強調した。楽器を持って集団で各地を遍歴し、先ざき( 行く先)でキャンプをはり、いにしえの歌や民謡を歌うこの若者文化は、20世紀ドイツの各方面に強い影響をあたえた。この運動で強調された大地や故郷という概念は、自国の文化のアイデンティティを意味していた。この運動のなかで、民謡やバロック音楽、古楽器などが再評価されるのである。リュートやチェンバロといった楽器が復活し、「バロック音楽」という用語がはじめてもちいられるもこの時代である。
▶︎青年運動
19世紀末20世紀初期、青年を主体とする文化を主張した社会運動。広くはボーイ・スカウトの運動もこのひとつの現象。早くから政治運動と関連をもち、ドイツやイタリア、チェコなどにおいてさまぎまに展開された。社会的にとくに大きな意味をもったのはドイツでの運動で、故郷や民族性を強調する立場からドイツの民謡や古楽、古楽器の復興に努めるとともにロマン主義を再認識。「ワンダーフォーゲル(渡り鳥の意)」はドイツにおける青年運動の象徴的な現象。やがて国家主義的な色彩を強くし、その一部はヒトラーユーゲントへと組み入れられていった。
この運動はドイツ・ロマン主義にも新たな目を向け、アイヒエンドルフやノヴァーリスといつたロマン派の詩人の芸術や思想がふたたび脚光を浴びる。しかし、失われた故郷と自然と大地をセンティメンタルに賛美するロマン主義の芸術は、二〇世紀初期の雰囲気のなか、ある種の危険な側面もはらんでいた。理想的なまでに純化されたドイツ文化への敬慕は、国民思想あるいは国家思想と容易に結びつきやすい側面をもっていたからである。その典型を示す作曲家が、ハンス・プフィッツナーであった。
プフィッツナーがアイヒェンドルフの詩に作曲したカンタータ《ドイツ精神について》は、新しいロマン主義運動を背景にした作品である。この作品が作曲されたのは第一次世界大戦終結後の1921年であった。世界に冠たるドイツが敗北したことの憂いは、遠い19世紀初期ロマン派の芸術への憧れとなって表された。《ドイツ精神について》はそのタイトルに表されているように、ドイツ民族の故郷への憧れをも表明するものであった。この時代においていかに1800年前後のドイツが憧憬の対象とされたかは、この時代の美学思想をあつかった文献の多さからも指摘することができる。
モダニズムを拒否し、古き伝統をかたくなに守ろうとするプフィッツナーの美学は、オペラ《パレストリーナ》においても強く表明されている。1917年に初演されたこのオペラは、トレント公会議におけるパレストリーナを題材にした作品で、革新的なものやコスモポリタン的なものを否定して、古きよき伝統に創作の土台をもとめるという内容であるが、この作品は同時に政治音楽でもあった。トーマス・マンは著書『非政治的人間の考察』のなかでこの作品をとりあげ、このオペラが彼自身を含めて当時の多くのドイツ人に強い共感をあたえた点に、この作品と時代の危機を読みとり、死への共感の危険性を指摘するのである。
▶︎ハンス・プフィツツナー
ドイツの作曲家、指揮者ロマン主義的な作風で知られ、1917年ヴァルターの指揮で初演されたオペラ《パレストリーナ》は大成功をおさめた。国粋主義的、反ユダヤ的な言動でも知られる。同時に政治音楽でもあった。トーマス・マンは著書『非政治的人間の考察』のなかでこの作品をとりあげ、このオペラが彼自身を含めて当時の多くのドイツ人に強い共感をあたえた点に、この作品と時代の危機を読みとり、死への共感の危険性を指摘するのである。
プフィッツナーは第一次世界大戦を熱狂的に支持し、潜水艦による無差別攻撃を推進することを提唱したテイルビッツ将軍を称えて、アイヒエンドルフの詩による歌曲《嘆き》を作曲する。ドイツ文化にあくまでも忠実であろうとし、異文化にはけっして心を開こうとしなかったプフィッツナーの偏狭さは、この時代のドイツの一面を代表していた。プフィッツナーの支持した無差別潜水艦攻撃の犠牲になったのが、スペインの作曲家エンリケ・グラナドスである。1916年、アメリカでおこなわれたオペラ《ゴイェスカス》の初演にのぞんだ後、イギリスの汽船サセックス号で帰国する途上、イギリス海峡でドイツの潜水艦の攻撃を受けて撃沈され、妻とともに帰らぬ人となったのである。
第一次世界大戦に敗れたドイツには進駐軍が駐留した理想のドイツ文化に固執していた当時のドイツは、諸外国の異文化との接触にことのほか過敏に反応した。とくにフランスが統治下のセネガルの兵士をドイツに駐留させたとき、ドイツ国内で起こつた反応は異常であった。自国に進駐軍として黒人が入ってきたことに、人びとは強いアレルギー反応を起こしたのである。
▶︎マン(1875-1955)
ドイツの作家。『ブッデンブローク家の人びと』でノーベル文学賞。ほかに『トーニオ・クレーガー』『魔の山』など。保守主義からリベラルな民主主義へ転向、ナチスが政権を掌握後スイスへ亡命、国外からドイツ国民にナチズムヘの不服従を訴えた。
ヒンデミットの師でもあるベルンハルト・ゼクレスは、むしろドイツの音楽文化の活性化のためにジャズを音楽教育にとりいれた。しかし、それは音楽関係者たちをこえて政治家たちからの強列な批判をかい、たんなる音楽教育のことがらが国会問題にまで発展するのである。ドイツの国民意識は一九世紀におけるプロイセンを中心とした国家形成の過程で醸成されていった部分が大きいが、ジャズなどの異文化はこのドイツ文化の純粋性をそこなうものであるという反感を買ったのである。ゼクレスによるジャズ教育の導入にたいして、プロイセン州議会でこのような質問がだされた・・・「国務省は、この「ホーホ]音楽院によるドイツ音楽の黒人化を阻止する用意があるのか。また、生徒たちを学長の衝動的で非ドイツ的な教育策からどのように守るつもりがあるのか」。
ドイツが自国に非西洋的要素が混入することに示したアレルギーは、フランスにはみられない現象であった。ジャーナリズムはまたこのジャズ音楽の導入を「黒人の血の輸血」とよんで、社会の関心を煽りたてる。議会の質問事項となり、ジャーナリズムをにぎわせたことにみられるように、このアレルギーは一部の人びとの反応ではなく、この国全体の意識を代弁していたとみられる。ジャズ批判は同時にアメリカ文化批判をも含んでいた。ミュンヒェン音楽アカデミー学長のハウゼッガーがジャズ教育の導入を「アメリカの大都会での生活によって堕落し、劣悪化された民族音楽である、そのような汚染された輸血にわれわれは感謝する」と皮肉たっぷりに述べるとき、彼は世論の多くを代表していたのである。
▶︎カグラナドス 1867-1916
スペインの作曲家。ピアニストとLても活躍。民族主義的で個性的なピアノ曲と歌曲を残す‥グラナドス音楽院を設」化して後進の育成にもあたった。
▶︎ゼクレス 1872-1934
ドイツの作曲家、教育者、指揮者。フランクフルトのホーホ音楽院でヒンデミット、アドルノらを育てる。一九二八年同音楽院にてジャズの講座を開く。
このような風潮に抗するように1922年、ヒンデミットは組曲《一九二二年》を作曲し、同年初演する。この組曲は(行進曲)(シミー)(夜曲)(ボストン)(ラグタイム)からなり、当時のドイツにおけるジャズ受容をもっともよく示している。エルヴィーン・シュールホフやエルンスト・クルシェネクらもジャズに新鮮な魅力を感じとり、自身の作品にその語法を導入したが、これらの音楽は批判の対象となった。当時のドイツにおけるジャズを題材にした作品のなかでの彗同傑作は、クルシェネクのオペラ《ジョニーは演奏する》である。この作品はジャズ・オペラとして二人センセーションを巻き起こし、人びとの喝采を受けたものの、同時に「国際主義」の名のもとに強い批判の対象とされ、やがてナチスの時代になると「退廃音楽」に分類されることになる。ユダヤの星を付した黒人がサクソフォンを演奏する絵に象徴的に描かれているように、異文化にたいするこの非寛容さは反ユダヤ思想との結びつきを示した。
▶︎退廃音楽
1930年代ナチス・ドイツが退廃的であるとみなした音楽の総称。メンデルスゾーン、シェーンベルク、マーラー、クルシェネク、アイスラー、ヒンデミット、ベルクなどの音楽がそれぞれ「ユダヤ的」「ジャズ的」「社会主義的」「前衛的」などのレッテルを貼られて弾圧された。
▶︎ハウゼッカー(1872-1948)
ドイツの指揮者。ミュンヒエンのカイム管弦楽団およびフランクフルト、グラスゴー、エディンバラ、ハンブルクなどで指揮活動後、1921年からミュンヒエン演奏協会管弦楽団(現ミュンヒエン・フィル)指揮者およびミュンヒエン音楽アカデミー学長。同アカデミーで教えたひとりがギユンダー・ヴァント。
▶︎ヒンデミット
(Paul Hindemith、1895年11月16日 – 1963年12月28日)は、ドイツ・ハーナウ出身の作曲家、指揮者、ヴィオラ奏者。その他にもヴァイオリン、クラリネット、ピアノなど様々な楽器を弾きこなす多才な演奏家であった。第一次世界大戦後、ロマン派からの脱却を目指し、新即物主義を推進。20世紀ドイツを代表する作曲家として同時代の音楽家に強い影響を与えた。また生涯に600曲以上を作曲。交響曲やオペラばかりではなく、オーケストラを構成するほぼすべての楽器のためのソナタを作曲した。
▶︎シュールホフ (1894-1942)
チェコの作曲家‥レーガー、ドビ ュッシーらに師事。ジャズとダダイズムの影響を受ける。一一九一九年ドレスデンて前衛的な連続演奏会を主催
▶︎クルシェネク (1900-1991)
オーストリア生まれのアメリカの作曲家‥一九二七年《ジョニーは演奏する》で大成功。ヴィーン国立歌劇場委嘱の《カール五世》は政治的理由で上演中止となる。その後渡米。さまぎまな様式による多数の作品を残した。
■ラヴェル《クープランの墓》とドビュッシー《英雄の子守歌》・・フランスにおける反ドイツ感情
近代フランス音楽は、ドイツ音楽の摂取から始まった。演奏会ではドイツの器楽が圧倒的な人気を博した。作曲面でもドイツの器楽が積極的にとりいれられていった。しかし、普仏戦争時においてドイツ音楽への批判が起こつたのと同様に、第一次世界大戦時においてもドイツ音楽受容の是非をめぐる論争が巻き起こる。
このとき、批判の矢面(やおもて)に立たされたのは、ヴァーグナーの音楽に理解を示していたフランキスト(セザール・フランクおよびその系統の作曲家)ではなく、またしてもサンサーンスであった。彼はこれまでドイツの器楽様式をとりいれ、ベートーヴェンやリストの音楽を深く理解し、均整のとれた古典的な様式の作品を作曲してきたが、その姿勢が「ドイツ贔屓(びいき)」と人びとの目に映ったのである。また、サンサーンスへの批判は、彼の音楽や思想というよりも、彼個人に向けられている面が大きいが、おりしも反ドイツの機運のなかで、サンサーンス批判が頂点に達するのである。
彼はプロイセンから「有功勲章」を受けていたが、彼は「プロイセンが攻めてきたら、有功勲章の叙勲者として人質にとられる恐れがある」と身の不安を述べなければならないような微妙な立場に立たされていた。戦線の火蓋(ひぶた)が切って落とされると彼は、愛国心からドイツ文化や音楽、とくにヴァーグナーを批判してこのようにのべた。
人びとはドイツ語を好まないし、しやべりたくも歌いたくも、習いたくもない。でも人びとはヴァーグナーの音楽を欲している。・・・女子供の虐殺、病院爆撃、教会の破壊、人間の尊厳にもとる悪行、フランスへの皮肉に満ちた嫌悪が表明された後に、ドイツがひさしく国民的天才とみなしてきた人物の音楽をもとめるフランス人がどうして存在しうるのか。
この文章は、サン・サーンスが「ドイツ贔屓(びいき)」というタイトルで著した批評文の二即で、明らかにセザール・フランクのグループ(フランキスト)を批判している。しかし、この「ドイツ贔屓」という批判が、逆にサン=サーンス自身に向けられるのである。「わたしにとってはフランスがいちばん、音楽はその次だ。フランス人が苦しんでいるときに、歌などうたえるだろうか」と自身が愛国者であることを表明しても、彼にたいする批判の大合唱の前にかき消されてしまう。戦争がはじまると、彼は創作を意図的に抑制していたかにみえる。わずかに歌曲や、トロンボーンとピアノのための《カヴァティーナ》などが書かれたが、そのわずかな作品すら批判の対象となったモーリス・ラヴェルはこの戦争に志願するが、体格が小さいことなどの理由で、輸送自動車部隊に配属される。トラック輸送部隊の隊員となったものの一九一六年、赤痢に罹患(りかん)して病院に収容される。野戦病院から友人のジャン・マルノールに宛てた手紙のなかで、彼はサン=サーンスをこう批判する。
▶︎フランク
ベルギー生まれのフランスの作曲家、オルガニスト。ピアニストとして活動後サントークロティルド教会オルガニストとなる。1872年パリ音楽院オルガン科教授となり多くの弟子を育てる・・86年国民古楽協会会長(作曲家としては晩年に多くの傑作を生みだしたきり
サン=サーンスはたくさんの魅力的な作品を発表したとききました。彼は戦争中に、舞台音楽、歌曲、悲歌、トロンボーンのための作品を作曲したそうですね。そのようなことはせずにそれらの作品のかわりに、榴弾(りゅうだん)の薬莢(やっきゃう)をあつかっていたら、音楽もそれでもっといいものになったでしょう。
すべてはこのナショナリズムの感情的な高まりのなかで進行していった。サン・サーンスへのこれらの批判は、この時代のフランスの動揺した社会を映しだしている。
フランス国内の反ドイツ感情は、とくにドビュッシーとラヴェルにおいて音楽作品のかたちで表現された。ドビュッシーの<英雄の子守歌》は「ベルギー国王アルベール一世陛下とその兵士たちを称えて」という副題をもつピアノ作品である。一九一四年に作曲されたこの作品は、ドイツ軍が中立国であるベルギー領内を通過したことにたいして、ベルギーが武力で対抗したことを称えて作曲されたもので、彼の最晩年の作品のひとつとなった。ラヴェルは《クープランの墓》の作曲にあたって、組曲を構成する6曲それぞれを第一次世界大戦で亡くなった若い人びとに捧げた。第一曲〈プレリュード〉は「ジャック・シャルロ中尉の思い出に」、第二曲の〈フーガ〉は「ジャン・クルップ少尉の思い出に」、第三曲の〈フォルラーヌ)は「ガブリエル・ドリユツク中尉の思い出に」、第四曲の〈リゴードン〉は「ピエールとパスカル・ゴーダン兄弟の思い出に」、第五曲の〈メヌエット〉は「ジャン・ドレフュスの思い出に」、第六曲の(トッカータ〉は「ジョゼフ・ド・マルリアーヴ大尉の思い出に」それぞれあてられている。この作品で、ラヴェルは、フランスのもっとも美しい精神を、もっとも美しく描くことによって、フランス文化の伝統の不滅を表現しょうとしたのである。
▶︎ラヴェル(1875-1937)
フランスの作曲家。ローマ賞に計五回挑戦しながら選にもれ、擁護者の抗議がバリ音楽院院長辞任へと発展、ラヴェル事件とよばれた。さまぎまなジャンルにおいて、古典主義的な形式感と洗練された書法と楽器法に裏打ちされながら斬新な響きをもつ傑作を発表した。
▶︎ビュッシー(Claude Achille Debussy, 1862年8月22日 – 1918年3月25日)
フランスの作曲家。長音階・短音階以外の旋法と、機能和声にとらわれない自由な和声法などを用いて独自の作曲を実行し、その伝統から外れた音階と半音階の用い方から19世紀後半から20世紀初頭にかけて最も影響力を持った作曲家である。ドビュッシーの音楽は、代表作『海』や『夜想曲』などにみられる特徴的な作曲技法から、「印象主義音楽(印象派)」と称されることもある。しかし、本人は印象主義音楽という概念に対して否定的であり、テクスト(詞)やテーマの選択は象徴派(象徴主義)からの影響が色濃い。
■エルガー《イギリス精神》-イギリスにおける反ドイツ感情
一九世紀のイギリスはもっとも熱心にドイツ音楽を受容した国であった。バッハ受容もきわめて早い時期から始まっており、ベートーヴェン熱だけでなく、メンデルスゾーンについてはイギリスの国民的な作曲家という地位すら獲得するにいたっており、ブラームスの音楽はスタンフォードらイギリス人作曲家たちによって高く話され、彼の作風はスタンフォードの理想となっていた。
ドイツ音楽を理想化する傾向はエドワード・エルガーにもひきつがれ、彼はプラムスとヴァーグナーの音楽書法をしっかりと継承していった。遅咲きのドイツ音楽とも形容できる、荘重で栄光に彩られた彼の作品は、大英帝国の栄華を映しだしているかのような音調をもつ。エルガーはリヒヤルト・シュトラウスに認められ、作曲家としての地歩を築いた。
▶︎エルガー(1857-1934)
イギリスの作曲家。独学で作曲を学び、合唱曲や《エニグマ・威風堂々》などの管弦楽曲で名声を得るロンドン交響楽団の指揮者としても活動した。
第一次世界大戦が始まると、国民的作曲家エルガーはいやがうえにも政治の渦中に巻きこまれる。1916年に作曲された合唱作品《イギリス精神》や1917年に作曲された《艦隊の攻撃》は、彼の時事的な作品を代表するものである。しかし、彼が第一次世界大戦における変動のなかでとくに心を砕いたのは、むしろポーランド問題であろう。エルガーはピアニストのパデレフスキが展開していたポーランド独立運動に共鳴していた。パデレフスキに献口重した交響的前奏曲《ポロニア》は、ポーランド難民救済基金のために作曲した作品である。
この戦争は思わぬところでイギリスの音楽界を困惑におとしいれる。戦争の影響でドイツ製のすぐれたピアノが入ってこなくなったのである。19世紀後半からピアノ製造界では、鉄骨フレームと交差張弦をとりいれるべきかで大きく会社の方針が二分され、積極的にこれらをとりいれていったアメリカのスタインウェイやドイツのべヒシュタインと、とりいれるのを拒否したフランスのエラールやイギリスのブロードウッドが対立していた。しかし、鉄のフレームや交差張弦の採用を、弦の自然な振動と共鳴をそこねるという理由で拒んだブロードウッド社は、近代のピアノ音楽の表現に適合しなくなっていっただけではなく、ピアノ教育界からもかえりみられなくなっていった。20世紀に入ると、ドイツ製のピアノとイギリスのブロードウッド社のピアノとの優劣はすでに明らかで、ブロードウッド社は完全に製品の競争力を失ったばかりか、ピアノの演奏や教育においてすら実用には適さないとみなされていく。
■<スタートからベヒシュタインDでの演奏比較、4:40あたりからスタインウェイDでの演奏に切り替わります。この動画で両者の特徴が非常に出ていると思います。>
第一次世界大戦が始まると、ギルドホール音楽学校など有力な学校では国家の方針に従ってドイツのピアノ使用禁止をうたったが、近代的な奏法や演奏表現にもはや適合しない旧式のピアノでは教育にも支障をきたす。そこで面白い現象が起こるのである。ドイツ製ピアノが第三国を経由してイギリス国内に輸入され、そのピアノには高いプレミアがつけられた。いわゆる「ころがし」すなわち転売するごとに値段を吊り上げて利益を生みだす現象がみられるようになったのである。
当時、ベヒシュタインやブリュートナーという大メーカーを擁するドイツにおいてはピアノ製造業は一大輸出産業となっており、その多くがイギリスおよびイギリスの旧植民地諸国で販売されていた。この戦争は、イギリスおよびとくにピアノの需要の高かったオーストラリアへのピアノ輸出が困難になったドイツのピアノ・メーカーにとつても打撃であった。戦争が始まるとドイツのメーカーは第三国を経由してイギリスにピアノを販売することを余儀なくされたのであった。
▶︎アレクサンドル一世(1777-1825)
ロマノフ朝ロシアの皇帝 (在位 1801-1825)、ポーランド立雀王内切代国王 (在位-1815-1825)、フィンランド大公国初代大公(在位1809-1825)
▶︎リヒヤルト・シュトラウス(1864-1949)
ドイツの作曲家、指揮者。ミュンヒェン大学生のころ大指揮者ビューローに作品が認められ指揮者としての活動を始める。一八八九年《ドン・フアン》の大成功ののち交響詩をたてつづけに発表。世紀が変わるとオペラの分野に進出、《サロメ》《エレクトラ》で名声を決定づけた。指拝者としてはミュンヒエン歌劇場、ベルリン王立歌劇場、ヴイーン国立歌劇場の監督を歴任し、モーツァルトを得意とした。






