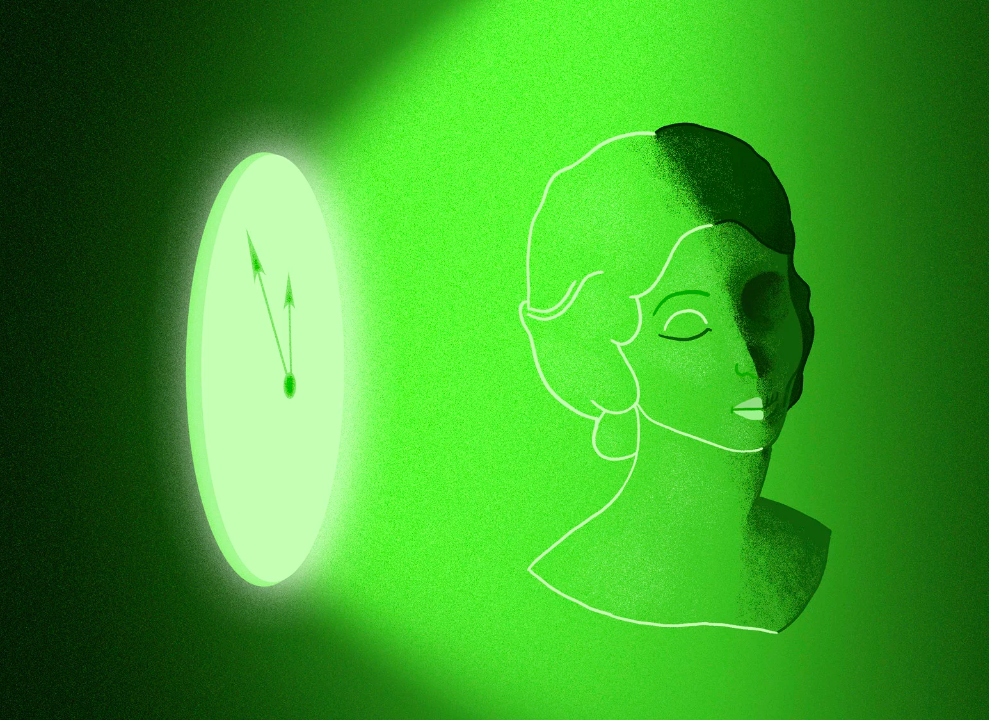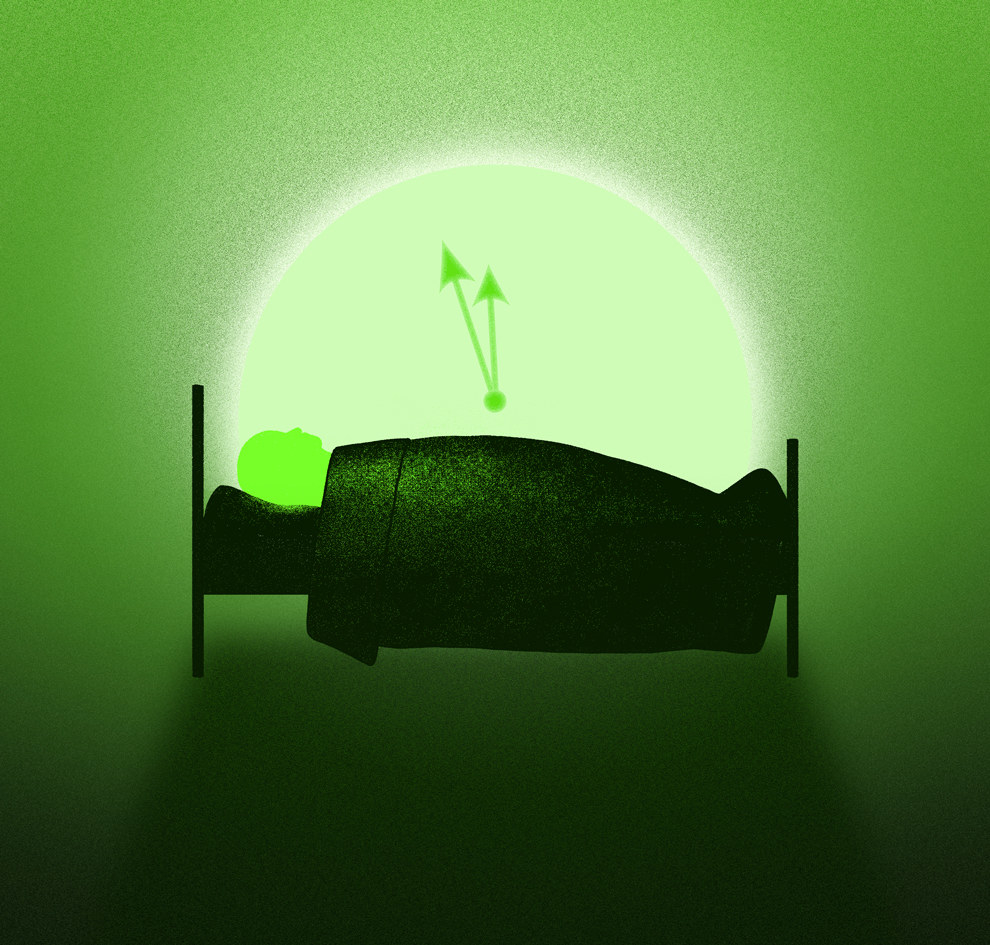■「ラジウム・ガールズ」、その忘れられた物語
勤務時間が終わると、女工たちの体は暗闇で光った。恐ろしい副作用が出てきた時、彼女たちは残された時間の中で、正義のために闘い始めた
1917年4月10日、18歳のグレイス・フライヤーは、ニュージャージー州オレンジにある米国ラジウム・コーポレーション(United States Radium Corporation, USRC)で、文字盤に塗料を塗る工員として働き始めた。米国が第一次世界大戦に参戦して4日が経っていた。ふたりの兄が戦争に行っていたグレイスは、国の役に立つことなら何でもしたかった。この新しい仕事が、自分の人生を、そして労働者の権利を永遠に変えることになろうとは思いもしなかった。
■ゴースト・ガールズ
戦争が始まると、何百人もの労働者階級の女性たちが工場に集まってきた。ラジウム入りの塗料で、腕時計や軍用時計の文字盤を塗る作業のために雇われたのだ。ラジウムは、マリー・キュリーが発見してからまだ20年もたっていない新しい物質だった。
文字盤を塗る作業は、「貧しい労働者階級の女性たちにとって、エリートの仕事」だった。賃金は平均的な工場の仕事の3倍以上で、幸運にもその仕事にありついた女性たちは、全米の女性労働者の上位5パーセントに入るほどの報酬をもらい、女性の権利が発展していく時代の中で、経済的な自由を得た。女工たちの多くは、細かい作業にうってつけの小さな手をしたティーンエイジャーで、友だちや家族を介して新しい仕事の魅力を広めた。工場では、一家の兄弟姉妹が揃って働く姿もよく見られた。
ラジウムの発光も魅力のひとつだった。文字盤を塗る女工たちは、すぐに「ゴースト・ガールズ」として知られるようになった。というのも、勤務時間が終わるころには、彼女たち自身が暗闇で光るようになっていたからだ。彼女たちはこの仕事を最大限利用し、よそ行きの服を着て工場で働いた。そうすれば、その服が夜のダンスホールで光るからだ。歯にラジウムを塗る者までいた。にっこりすれば相手を虜にできた。
グレイスも同僚たちも、教えられた通りのやり方で、ときには幅が3.5センチしかないような小さな文字盤を塗る、骨の折れる手作業を行った。女工たちは、唇でくわえて筆を整え、先を細くするよう教えられた。「lip-pointing(唇で整える)」あるいは、劇作家のメラニー・マーニッチがのちに「lip, dip, paint routine(くわえる、舐める、塗る、の繰り返し)」と描写した作業だ。筆を口に持っていくたびに、女工たちは光る緑の塗料を少しずつ飲み込んでいた。

■真実と嘘
「最初に私たちが尋ねたのは、『体に害はないのですか?』でした」。グレイスに作業のやり方を教えたメイ・カバリーは、当時を思い出してそう語った。「体に悪いようなものは、当然口に入れたくないですから。(マネージャーの)サヴォイさんは、『危険なものではないから心配しなくていいよ』と言いました」
だが、それは真実ではなかった。この光る物質が発見されたときから、体に害があることは知られていたのだ。マリー・キュリー自身も、ラジウムを素手で扱ったために放射線熱傷を負った。女工が文字盤を塗る筆を持つ前に、ラジウム中毒で亡くなった人はいたのだ。
ラジウム会社の男性たちが、研究所で鉛のエプロンをつけ、ラジウムを扱うときには先端が象牙でできたトングを使ったのはそのためだった。だが、女工たちにはそのような防護は用意されなかったし、そうした防護が必要かもしれないという警告さえなかった。
なぜなら当時は、女性たちが扱っていたくらいの少量のラジウムは、健康に良いと信じられていたからだ。ラジウム水は強壮剤として飲まれ、この魔法の物質が入った化粧品やバター、牛乳、歯磨き粉などが売られていた。新聞は、ラジウムで「長生きできる」と報じた。
だが、こうした考えの基になった研究報告は、ラジウム産業で潤うラジウム会社が実施したものだった。彼らは「危険」を示すあらゆる兆候を無視した。女工たちに問われれば、「ラジウムは頬をバラ色にしてくれるよ」とマネージャーたちは言った。

■ひとり目の死
1922年、グレイスの同僚のひとりモリー・マッジャが、仕事をやめなければならなくなった。病気になったのだ。何が原因なのか、自分でもわからなかった。始まりは歯痛だった。歯医者で抜いてもらうと、今度は隣りの歯が痛くなり、それも抜いてもらわねばならなくなった。歯を抜いたところには、ひどい潰瘍ができた。血の赤と膿の黄に染まった邪悪な花のようだった。たえず膿が出て息が臭くなった。それから四肢の痛みに襲われた。あまりの痛みに、ついに歩けなくなった。医者はリウマチと診断し、アスピリンを与えて家に帰した。
1922年5月には、モリーの状態は絶望的になった。そのときには、歯はほとんどなくなり、正体不明の感染症は広がっていた。下顎全体と口蓋、それに耳の骨の一部までが、「1つの大きな膿瘍」と診断された。だがそれだけでは終わらなかった。歯科医が口の中の下顎の骨を指でそっと突いたところ、恐ろしいことに骨が崩れてしまったのだ。歯科医は骨を取り除いた。「手術でではなく、ただ口の中に指を入れ、つまんで取り出した」のだ。わずか数日後、下顎全体が同じようにして取り除かれた。
モリーは文字通り崩れつつあった。そしてそれは、モリーだけではなかった。そのときまでには、グレイス・フライヤーも顎に異常が出ており、足の痛みに苦しんでいた。ほかのラジウム・ガールズたちも同じだった。
1922年9月12日、モリー・マッジャを1年近く苦しめてきた奇妙な感染症は、のどの組織にまで広がった。病はゆっくりと頸静脈を侵していった。同日午後5時、モリーの口の中は血であふれた。急速に出血が進み、看護師の止血が間に合わなかった。モリーは24歳でこの世を去った。医師たちは死因を特定できずに困惑し、死亡証明書には「梅毒」という誤った病名が書かれた。この病名は、彼女が働いていた会社ものちに使うことになる。
ほどなく、まるで時計仕掛けのようにひとりずつ、かつての同僚たちがモリーのあとを追っていった。
■隠 蔽
雇い主のUSRCは、彼女たちの死に対する一切の責任を、2年近く否定し続けた。しかし、USRCの言う「ただの噂」はなかなか消えず、業績が悪化した。1924年、ついに同社は専門家に依頼して、噂されている「文字盤を塗る作業」と「女性たちの死」の関連性を調べた。
ラジウムの良さを謳ったUSRC自身による調査報告とは異なり、今回の調査は独立したものだった。そして、専門家がラジウムと女性たちの病気は関係があることを認めると、ラジウム会社の社長は激昂した。調査結果を受け入れる代わりに、社長は新たにいくつかの研究に金を払った。正反対の結果が発表された。社長は、最初の研究報告の結果について調査を始めていた労働省に対しても、嘘の報告をした。社長は、女性たちが病気を「会社のせい」にしようとしているとして公然と非難し、増え続ける医療費に苦しみ、経済的な援助を得ようとする彼女たちを罵倒した。
■光は嘘をつかない
調査結果がもみ消されたため、謎の病と、彼女たちが日に何百回も摂取していたラジウムとの関係を証明することは最大の障壁となった。彼女たちは、責めを負うべきは会社だと主張したが、闘う相手は、広く浸透しているラジウムの安全神話だった。事実、専門家たちがこの件に向き合ったのは、ラジウム会社でひとり目の男性従業員が亡くなってからだったのだ。1925年、ハリソン・マートランドという優秀な医師が、自身が考案したやり方で、ラジウムが女工たちに害を与えたことを決定的に証明して見せた。
さらにマートランド医師は、女工たちの体内で何が起こっているのかも説明した。ラジウムが体の表面についた場合、劇的な害を及ぼす可能性があるということは、1901年にはすでに分かっていた。ピエール・キュリーはかつて、重量1キログラムの混じりけのないラジウムと同じ空間にいたいと思わない、と言った。体中の皮膚がやけどを負い、目はつぶれ、「(自分は)おそらく死ぬことになるだろう」と考えていたからだった。マートランド医師は、ラジウムを体内に取り入れると、たとえそれがごくわずかであっても、体に及ぼす害は何千倍も大きいということを発見した。
経口摂取したラジウムは、女性たちの体の中で定着し、たえず破壊的な放射線を出すようになり、骨を「穴だらけにしてしまう」。生きながらにして、まさに体中にたくさんの穴があくのだ。女性たちは体中が侵されていた。グレイス・フライヤーの背骨は「つぶれて」、背中を固定するためのブレースをつけなければならなかった。別の女性は顎が浸食され、「根元の部分だけ」しか残っていなかった。女性たちの脚は短くなり、自然に骨折してしまうこともあった。

さらに、ダメージを受けたこうした骨は、内部に定着したラジウムのせいで、気味の悪いことに光を放ち始めた。それは、真実を語る光だった。ときには、夜中に鏡に映った自分の姿を見て、ラジウムに侵されていることを知る女性もいた。鏡の中の姿が幽霊のように光っていたからだ。不自然な発光は運命を告知するものだった。
というのもマートランド医師によると、体への害は致命的なものだったからだ。ラジウムは体の中にあり、彼女たちの骨からそれを取り出すすべはなかった。

ラジウムで顎に肉腫ができた文字盤塗装の女工。正面と横からの写真。